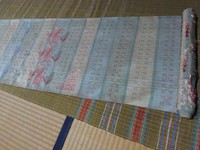前と後ろ→その1
ある日、
TV朝日のナニコレ百景という番組に、具志堅用高が登場してきた。その中で、山城さんによるマラソン大会が放映していました。

沖縄県うるま市石川字山城という部落には、8割『山城さん』が住んでいて、部落の名前も住んでいる人も『山城』という番組でした。そこで自分は、どうして ? ‥そんなに『山城』という名前にこだわるのか ?‥ 不思議に思いました。

山城は『お茶』の産地になっていました‥

山城は、旧・石川市 (今は、うるま市) の中にあつて近くには、『伊波城』⇔反対側の恩納村には、『山田城』がありました。
自分はその、伊波城と山田城は同じ「隠れ」平家の里ではないのか?‥思っています。そして、旧・石川市と恩納村は沖縄島の中央構造線・フォッサマグナのような感じでした。

その辺りは、沖縄島のウエストのように細い所で、埋め立て地を省くと地図帳よりも細くなっています。

またその辺りから、南北にして農作物、石、土、人? など‥性格が違うという説があります。

旧・石川市の伊波城と恩納村の山田城には、今帰仁 (なきじん) 城から逃げて来た人々が住んでいました。*伊波城と山田城は身内どうしの関係です。そして、今帰仁城の大手門の別名は「平朗門? / 平家門」とも呼ばれ、今帰仁城は『平家の落人』が建てた城‥と、いう説があります。
今帰仁城 (平家城?‥) から逃げて来た山田城主・護佐丸盛春の「盛」という文字もまた平家の落人がよく使う名前です。
*護佐丸盛春 http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B7%E4%BD%90%E4%B8%B8

その辺り (沖縄島のウエストライン) は、北山国 (本店・今帰仁城)と中山国 (本店・首里城) との攻防が続きました。
ー(・・?ー・ー

日本島の中央構造線・フォッサマグナを辺りにして、植物、動物、昆虫→ゲンジボタルの点 滅など‥性格が違うといいいます。
日本島の中央構造線・フォッサマグナ (不破の関辺り) では、近世には「関ヶ原の戦い」⇔ 古代では「壬申の乱」 という『東西の戦い』が起きました。*「壬申の乱」のポイントには『蘇我倉山田石川麻呂』の存在がありました。

旧・石川市にある『伊波城』と恩納村にある『山田城』を合わせると→蘇我倉山田石川麻呂→南朝の里のようにも見えてきます。*主に、山城国は「北朝 」⇔ 大和国は『南朝』‥と、いう時代がありました。
伊波城 (旧・石川市) と山田城 (恩納村) は、 南朝の落ち武者と平家の落人が隠れている『城』だ‥と、自分は「もうそう」と仮説→『もう説』をたててみました。
恩納村にある万座毛 (まんざもう) という崖 (ばんた) では、毛遊び (もうあしび) という『月星信仰』は、京都府の宇治で行われる県 (あがた) 祭りと似ていました。*宇治山田茶?‥という名前も気になりますが、その京都府の宇治は昔、『山城国』でありました。
ー(・・?ー・ー
南北朝時代~室町時代、山城国は「北朝」⇔ 大和国は『南朝』‥でありました。
室町幕府 (北朝) の足利尊氏は、

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A2%E7%AA%93%E7%96%8E%E7%9F%B3 夢窓疎石という僧侶の勧めで南朝 (吉野朝) の怨霊信仰ため、天竜寺船→ http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E9%BE%8D%E5%AF%BA%E8%88%B9 ←という寺社造営科唐船を出していました。
(・・? つまり?‥ 室町幕府 (山城国) の前 (政治) は「北朝」⇔後ろ (祭祀) は『南朝』?‥のような感じになっていました。
ー・ー
またある日、TV朝日のナニコレ百景という番組に、草を食べる俳優が登場してきた。その中で、周防国上関町にある祝島 (いわいしま) が出てきて、3代に渡って石垣を積み重ねて、ようやく『畑』を造ったと放映していました。

その事から、祝島は古くから農業が難しい島だと見えてきます。
古代の『租・庸・調』~近代の『士農工商』まで、農業を主税とする『農本主義』を敷いていたので、農業が難しい地域は、海の『交換場』に参加していたと思います。
祝島 (いわいしま) は、万葉集では『伊波比島』と記されていました。
島の特色には『上関原子力発電所』の話題で知られています。そして、島の特産品には『枇杷茶』、『堅豆腐』など‥あり→似ている豆腐に、長崎県五島列島の『潮豆腐』や沖縄県糸満市の『石豆腐』が知られているという。http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9D%E5%B3%B6
また、『枇杷茶』の「びわ」について、長崎県 (肥前国) は日本一の「びわ」産地になっています。その事から、肥前国と周防国の共通点に『松浦水軍』の足跡が思い浮かびます。
松浦氏の租 (おや) と子孫には、安倍氏が含まれています。安倍氏は、上関町のとなり町→田布施にも住んでいました。
ー・ー
奥州 (今の東北地方) は「前九年の役」において、奥州安倍氏の生き残り 安倍宗任の三男・安倍季任 (あべのすえとう) は九州の松浦に行き、松浦水軍の松浦氏の娘婿となり「安倍季任」は『松浦実任』と名乗りました。その後、色いろあって先祖・安倍宗任以来の旧姓・安倍姓に戻しました。
ー(・・?ー・ー
話し内容は、マニアックな展開になってきましたが、東国と西国、北朝と南朝、源氏と平家、前と後ろ→政治と祭祀など‥さまざま見えてきます。
その話は置いといて、再び話を『山城』に戻します。

山城の近くには、伊波 (いは) と嘉手苅 (かでかる) という部落があります。

その辺りは、鍛冶、製鉄に関する仕事が行われていました。嘉手苅 (かでかる) の語源1つに、「嘉手」は「勝手」を意味しており、古代に「カチ」と呼ばれていた地名が「鍛冶」→「製鉄業」→高温火力を扱う『カマド』→台所→「勝手」→竈門 (カマド) →釜戸→台所の戸を『勝手口』と?いうように?なったといいます。
苅(カル)は、古代語の火(フル)が火(ヒル)→火(カル)→火(ひ)→火(か)→『カル』だという説があり、 現代でも朝鮮語では「プル=火」で、 また苅(カル)は、嘉陽、賀陽、茅、伽揶、加羅とも、 あるといいます。http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1059354030
ー・ー
恩納 (おんな) 村の伊武部 (いんぶ) の反対側に ⇔ 名護市の辺野古 (へのこ) があります。

♀伊武部は凹んで ⇔ ♂辺野古は尖っています。*古い日本語で『へのこ』とは尖った 凸 もの ♂ 意味していたようです。

名護市辺野古はむかし、久志村の辺野古でした。久志 (くし) は串→辺野古はさらに尖った串 (くし) を意味しているのではないか?‥と、『もう説』をたててみました。
ー(・・?ー・ー
まだまだたくさん「あれ‥」と思う事がありますが、眠くなってきましたのでまた‥
あくまでもそれは、
「もうそう」と仮説 →『もう説』です。
TV朝日のナニコレ百景という番組に、具志堅用高が登場してきた。その中で、山城さんによるマラソン大会が放映していました。

沖縄県うるま市石川字山城という部落には、8割『山城さん』が住んでいて、部落の名前も住んでいる人も『山城』という番組でした。そこで自分は、どうして ? ‥そんなに『山城』という名前にこだわるのか ?‥ 不思議に思いました。

山城は『お茶』の産地になっていました‥

山城は、旧・石川市 (今は、うるま市) の中にあつて近くには、『伊波城』⇔反対側の恩納村には、『山田城』がありました。
自分はその、伊波城と山田城は同じ「隠れ」平家の里ではないのか?‥思っています。そして、旧・石川市と恩納村は沖縄島の中央構造線・フォッサマグナのような感じでした。

その辺りは、沖縄島のウエストのように細い所で、埋め立て地を省くと地図帳よりも細くなっています。

またその辺りから、南北にして農作物、石、土、人? など‥性格が違うという説があります。

旧・石川市の伊波城と恩納村の山田城には、今帰仁 (なきじん) 城から逃げて来た人々が住んでいました。*伊波城と山田城は身内どうしの関係です。そして、今帰仁城の大手門の別名は「平朗門? / 平家門」とも呼ばれ、今帰仁城は『平家の落人』が建てた城‥と、いう説があります。
今帰仁城 (平家城?‥) から逃げて来た山田城主・護佐丸盛春の「盛」という文字もまた平家の落人がよく使う名前です。
*護佐丸盛春 http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B7%E4%BD%90%E4%B8%B8

その辺り (沖縄島のウエストライン) は、北山国 (本店・今帰仁城)と中山国 (本店・首里城) との攻防が続きました。
ー(・・?ー・ー

日本島の中央構造線・フォッサマグナを辺りにして、植物、動物、昆虫→ゲンジボタルの点 滅など‥性格が違うといいいます。
日本島の中央構造線・フォッサマグナ (不破の関辺り) では、近世には「関ヶ原の戦い」⇔ 古代では「壬申の乱」 という『東西の戦い』が起きました。*「壬申の乱」のポイントには『蘇我倉山田石川麻呂』の存在がありました。

旧・石川市にある『伊波城』と恩納村にある『山田城』を合わせると→蘇我倉山田石川麻呂→南朝の里のようにも見えてきます。*主に、山城国は「北朝 」⇔ 大和国は『南朝』‥と、いう時代がありました。
伊波城 (旧・石川市) と山田城 (恩納村) は、 南朝の落ち武者と平家の落人が隠れている『城』だ‥と、自分は「もうそう」と仮説→『もう説』をたててみました。
恩納村にある万座毛 (まんざもう) という崖 (ばんた) では、毛遊び (もうあしび) という『月星信仰』は、京都府の宇治で行われる県 (あがた) 祭りと似ていました。*宇治山田茶?‥という名前も気になりますが、その京都府の宇治は昔、『山城国』でありました。
ー(・・?ー・ー
南北朝時代~室町時代、山城国は「北朝」⇔ 大和国は『南朝』‥でありました。
室町幕府 (北朝) の足利尊氏は、

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A2%E7%AA%93%E7%96%8E%E7%9F%B3 夢窓疎石という僧侶の勧めで南朝 (吉野朝) の怨霊信仰ため、天竜寺船→ http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E9%BE%8D%E5%AF%BA%E8%88%B9 ←という寺社造営科唐船を出していました。
(・・? つまり?‥ 室町幕府 (山城国) の前 (政治) は「北朝」⇔後ろ (祭祀) は『南朝』?‥のような感じになっていました。
ー・ー
またある日、TV朝日のナニコレ百景という番組に、草を食べる俳優が登場してきた。その中で、周防国上関町にある祝島 (いわいしま) が出てきて、3代に渡って石垣を積み重ねて、ようやく『畑』を造ったと放映していました。

その事から、祝島は古くから農業が難しい島だと見えてきます。
古代の『租・庸・調』~近代の『士農工商』まで、農業を主税とする『農本主義』を敷いていたので、農業が難しい地域は、海の『交換場』に参加していたと思います。
祝島 (いわいしま) は、万葉集では『伊波比島』と記されていました。
島の特色には『上関原子力発電所』の話題で知られています。そして、島の特産品には『枇杷茶』、『堅豆腐』など‥あり→似ている豆腐に、長崎県五島列島の『潮豆腐』や沖縄県糸満市の『石豆腐』が知られているという。http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9D%E5%B3%B6
また、『枇杷茶』の「びわ」について、長崎県 (肥前国) は日本一の「びわ」産地になっています。その事から、肥前国と周防国の共通点に『松浦水軍』の足跡が思い浮かびます。
松浦氏の租 (おや) と子孫には、安倍氏が含まれています。安倍氏は、上関町のとなり町→田布施にも住んでいました。
ー・ー
奥州 (今の東北地方) は「前九年の役」において、奥州安倍氏の生き残り 安倍宗任の三男・安倍季任 (あべのすえとう) は九州の松浦に行き、松浦水軍の松浦氏の娘婿となり「安倍季任」は『松浦実任』と名乗りました。その後、色いろあって先祖・安倍宗任以来の旧姓・安倍姓に戻しました。
ー(・・?ー・ー
話し内容は、マニアックな展開になってきましたが、東国と西国、北朝と南朝、源氏と平家、前と後ろ→政治と祭祀など‥さまざま見えてきます。
その話は置いといて、再び話を『山城』に戻します。

山城の近くには、伊波 (いは) と嘉手苅 (かでかる) という部落があります。

その辺りは、鍛冶、製鉄に関する仕事が行われていました。嘉手苅 (かでかる) の語源1つに、「嘉手」は「勝手」を意味しており、古代に「カチ」と呼ばれていた地名が「鍛冶」→「製鉄業」→高温火力を扱う『カマド』→台所→「勝手」→竈門 (カマド) →釜戸→台所の戸を『勝手口』と?いうように?なったといいます。
苅(カル)は、古代語の火(フル)が火(ヒル)→火(カル)→火(ひ)→火(か)→『カル』だという説があり、 現代でも朝鮮語では「プル=火」で、 また苅(カル)は、嘉陽、賀陽、茅、伽揶、加羅とも、 あるといいます。http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1059354030
ー・ー
恩納 (おんな) 村の伊武部 (いんぶ) の反対側に ⇔ 名護市の辺野古 (へのこ) があります。

♀伊武部は凹んで ⇔ ♂辺野古は尖っています。*古い日本語で『へのこ』とは尖った 凸 もの ♂ 意味していたようです。

名護市辺野古はむかし、久志村の辺野古でした。久志 (くし) は串→辺野古はさらに尖った串 (くし) を意味しているのではないか?‥と、『もう説』をたててみました。
ー(・・?ー・ー
まだまだたくさん「あれ‥」と思う事がありますが、眠くなってきましたのでまた‥
あくまでもそれは、
「もうそう」と仮説 →『もう説』です。
この記事へのコメント
面白い記事です。山城には奥にいくと、沖縄にしては高い山があり(ゴルフ場のある場所)不思議な場所です。あと、あまり知られていない軍の施設がある?私は直観でイエスが生きてた頃となにかしらの
繋がりを感じます。
神倭伊波礼毘古命(初代天皇神武天皇の名前。伊波が入ってますね)
繋がりを感じます。
神倭伊波礼毘古命(初代天皇神武天皇の名前。伊波が入ってますね)
Posted by たろう at 2016年07月26日 11:47
>たろうさん
はじめまして、
伊波礼彦
熊野信仰のヤタガラス (秘密結社) など
嘉手苅観音堂、製鉄の町。
闘牛の町 ← 牛頭天王? ← ミトラス教?
自分も何らかの信仰を持つ人々の名残りがあったように感じています。
はじめまして、
伊波礼彦
熊野信仰のヤタガラス (秘密結社) など
嘉手苅観音堂、製鉄の町。
闘牛の町 ← 牛頭天王? ← ミトラス教?
自分も何らかの信仰を持つ人々の名残りがあったように感じています。
Posted by 阿佐工房 at 2016年07月27日 14:08
at 2016年07月27日 14:08
 at 2016年07月27日 14:08
at 2016年07月27日 14:08