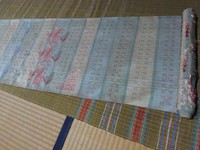辺境の地 → その2
民俗学者の柳田国雄氏は、
「桃太郎を甘く見てはいけない」 と、言っていました。そのほか → 「白山信仰には何かが隠れている」 と言い、何かを調べていたようです。
(・・;) 彼はその後、沈黙したという。
巷 (ちまた) で彼は『知りすぎた男』と云われている。
近年、桃太郎や金太郎、かぐや姫にカゴメ唄など‥ おとぎ話や童歌には 「敗者の思い」 が隠れていると話題になっています。
ー・→
ここから先、
推理小説ならぬ『推理もう説』をたて、その謎 (なぞ) を紐解いて見ようと思う。
ー(・・? ー・ー
まづ、
桃太郎は鬼退治に行く途中、どんどん仲間たちと出会い、仲間を引き連れ鬼退治へと向かいました。
山から都に降りて来た金太郎は、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7081411.html 地位は低くとも ⇔ 実力があれば、出世して武士になれるお話でした。けれども、金太郎が退治する鬼は、かつての自分の仲間たちと似ていた。
実は‥ 鬼退治した桃太郎も昔オニで、桃太郎が引き連れた仲間たちも昔オニであった‥ という説があります。
いつの日か、自分が亡ぼした鬼に滅ぼされ、滅ぼした鬼は亡ぼされた鬼の霊魂 (たましい) を背負って生きて行くお話です。

← 中央から → 離れれば → 離れるほど → 鬼が住んでいる。そうした恐怖心が大きな鬼を生んでいました。
ー・ー
これまでのお話とは、まったく関係ないのだが、

江戸城 北の丸の北に『飯田橋』という所があります。

飯田橋の北東に向かうと、小さい日向? → 小さい石川? → 白山通り → 不忍通り → 伊賀上野? 上野国? → など‥ ある出来事を連想する名前が満載しています。
前回のブログで、江戸城を作ったのは太田道灌 (おおたどうかん) だと載せていましたが、2回目に江戸城を作った人は藤堂高虎 (とうどうたかとら) という人でした。さらに、大阪城を2回目に作ったのも藤堂高虎 (とうどうたかとら) という人でした。*江戸城も大阪城も1期、2期と違う人が再興 / 復興している。
ー・→
藤堂高虎 (とうどうたかとら) は築城の先生で、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えました。高虎は特に石垣作りを得意とし、織田信長が安土桃山城を作る時にも参加していました。
築城技術に長けた藤堂高虎は、甲賀・忍者の里「近江国犬上郡藤堂村」で生まれ、外様大名として、伊予 → 伊勢 → 伊賀の上野 ~ 東京の上野?とも「引越し」をしています。*甲賀 ~ 伊賀の?上野? 忍者の里に?‥
余談ですが、
東京の「半蔵門」の名称は、徳川家康に仕えた服部半蔵が率いる「忍者の町」で、上野駅近くの不忍池や上野山は忍岡山とも呼ばれ、隠密 (おんみつ) の里であったと云われています。
ー(・・? ー・ー
もう一度、

『飯田橋』を東の川沿いに進むと → 水道橋 → 猿楽町 → お茶の水や湯島など‥『お茶色』地名が見られます。
ー・ー
*織田信長は、
比延山 (天台宗の聖地) を焼き → その後、加賀発の一向一揆 (浄土真宗の反乱) を成敗していました。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86
さらにその後に → 織田信長は高野山 (真言宗の聖地) を焼こうと計画している最中に 「本能寺の変」 にて亡ぼされた‥ とも云われています。*織田信長は最も寺社勢力に苦戦していた
近江国にある比延山 (天台宗の聖地) は藤堂高虎 (とうどうたかとら) の縁 (ゆかり) 里? ようにも見えます。*藤堂高虎は、甲賀・忍者の里「近江国犬上郡藤堂村」で生まれた ⇔ 織田信長は比延山を焼いた。
通説では、

飯田橋近くの『小石川』の語源は 「小石の川」 になっていますが、異説 / 小数説として、加賀の鳥越村 (今は石川県白山市) の一向宗 (浄土真宗) の信徒が飯田橋近くの『小石川』に住んでいたので‥ という説があります。*全国的に白山信仰が盛んだった地域は一向宗 (浄土真宗) の盛んな地域にスライドする場合が見られます。
ー(・・? ー・ー
もう一度、

飯田橋の近くには『後楽園』という庭園がありました。
庭園作りには、宗教的意味合い (穢土 ⇔ 浄土) 思想が含まれ、「穢れ / 汚れ」 を 「浄め / 清め」 る庭師が庭園作りをしていました。
日本庭園には、
平安時代に 「浄土式庭園」、室町時代に 「枯山水 (禅宗式庭園) 」、江戸時代には 「回遊式庭園」 が流行したようです。
江戸時代に作られた『後楽園』という庭園は 「回遊式庭園」 に分類され、 「回遊式庭園」 は → 「浄土式庭園」 と 「枯山水 (禅宗式庭園) 」 の集大成 (浄土式と禅宗式の折衷) になっているといいます。
浄土系の仏教には、浄土宗、一向宗 (浄土真宗) 、時宗など‥ 他力本願 (歩く仏教) ⇔ 禅宗系の仏教には、臨済宗、曹洞宗など‥ 自力本願 (座る仏教 / 座禅とお茶) という違いがあるようです。
浄土式と禅宗式の庭園は、宗教や宗派、思想上の違いがあるけど ⇔ ケガレをキヨメる庭師 (観阿弥や世阿弥など) には、共通性があるよう?‥ 気がします。
『飯田橋』を東の川沿いに進むと → 水道橋 → 猿楽町 → お茶の水や湯島など‥『お茶色』≒ 禅宗色地名が見られ ⇔ 北に進むと浄土色の地名が見られます。
つまり、ケガレをキヨメる職業をする人々が『後楽園』という庭園の近くに住んでいたのでは?‥ と、考えて見ました。
ー・→
人に対して ⇔ 鬼というのは失礼ではないか、と思う人もいると思いますが、一人ひとり心の中に鬼が住んでおり、自分とは関係ない。自分の不都合は見えない。無力感 → 無抵抗 → 無関心 → 長いにまかれて →
← 中央から → 離れれば → 離れるほど → 鬼が住んでいる。そうした恐怖心が大きな鬼を生んでいました。
あくまでもそれは、
「もうそう」 と仮説 →『推理もう説』
深い意味はありません。
この記事へのコメント
興味深いですね。仏教では修行中⇒菩薩、悟った人⇒如来と、最澄や空海など。またアメリカの作家ジェリー・ギリーズの名言に恐怖心と向き合い、それをリストアップし、中身を良く知れば、恐怖心を乗り越えて前進することができる。と書いてます。脱線したコメントですみません。
Posted by チョコチップバニラ at 2016年12月17日 22:09
at 2016年12月17日 22:09
 at 2016年12月17日 22:09
at 2016年12月17日 22:09