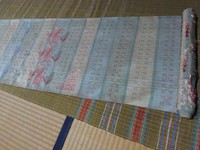デジャブる旅行
歴女の間では幸村 (ゆきむら) 様が人気を呼んでいます。

(’-’*)♪ ♀ ☆ ♪
幸村様は戦国武将の真田幸村 (信繁) の事で、

(’-’*)♪ 幸村様がイケメン (色男) であった事も歴女たちのトキメキ心を揺れ動かしています。
(’-’*)♪ ♀ ☆ ♪
真田幸村 = 真田信繁

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%B9%81
【 真田氏の家紋について 】

江戸時代に 真田幸村 (信繁) を取り上げた物語の影響で、真田氏 ≒「六文銭」の家紋。と事が定着したといいます。
真田氏の源流である海野氏は根津氏、望月氏と同じ『滋野3家』といい三家は緊密な関係でした。
☆ ♪ ★ ♪ ☆ ♪
【 滋野3家は月星紋 】
海野氏は、滋野氏の家紋である「月天七九曜 (月星紋)」にちなみ「月輪七九曜 (月星紋)」を家紋にしていたが、後ほど「六文銭」の家紋を使用するようになり、海野氏の分家である真田氏も「六文銭」の家紋を使用するようになったといいます。
ー?→
(・・? 気のせいか?

真田幸村 / 真田氏の家紋は、

打紙 (ウチカビ) に似ている気がしました。
ー?→
打紙 (ウチカビ) とは、
冥銭 (めいせん ≒ あの世の紙銭) の1種で、中国や台湾、韓国、ベトナム、琉球などにおいては、紙幣を模した冥銭が用いられ。祖霊信仰の一種で墓前で冥銭を焚いたり、特に旧盆の時期に祖霊への供物として軒先で焚かれる。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A5%E9%8A%AD と、ある。

沖縄県では打紙 (ウチカビ) と呼ばれる黄色い紙に銭形を押した紙銭 (カビジン) = 冥銭が一般的に用いられ、これらの副葬品は死者が「あの世でお金に困らないように」や「三途の川の渡し賃」などの意味があるといいます。
ー?→
(・・? また、
日本の仏教でも死者に『六文銭』を持たし、三途川を渡らせる。と風習があるようです。
三途川 (さんずのかわ) とは、

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%80%94%E5%B7%9D
此岸 (シガン ≒ この世)と彼岸 (ヒガン ≒ あの世) を分ける境目にあるとされる川で、
三途川の渡し船の料金は六文と定められており、六文銭 (冥銭) を持たせる習俗が?‥ とあり、日本では、三途川の渡河料金として六文が冥銭とされ、仏教の六道輪廻から『六文銭』が由来しており、それは貨幣経済の発達に伴い霊界でも貨幣が必要だという価値観念から、死後世界へと移行する通過儀礼的な意味合いを持ち、真田氏や海野氏が六文銭の家紋を使用する事で知られているようです。
ー?→
(・・? どうして?
真田氏や海野氏のは、死語世界を連想する『六文銭』の家紋を使用していた? いうと、戦場にあっても「死を恐れていない」という気概を相手に見せるため、旗印や鎧兜、袖の裾に三途川の渡し賃である六文銭を身につけていた。と考えられ、主に戦時に使用する家紋であったようです。
 ―…
―… →
→ →
→
(・・? 今となつて?!
真田氏や海野氏というと「六文銭」の家紋。と事を連想するけど、それは戦時用 (一時的) の お話で、真田氏は海野氏の分家と云われ、真田氏の源流である海野氏は根津氏、望月氏と同じ『滋野3家』といい三家は緊密な関係でした。
(・・? もとはというと?!
真田氏 → 海野氏、根津氏、望月氏という『滋野3家』は、月星信仰に通づ「月星紋 (家紋) 」を使用する駒人 (コマぴと) が祖とされ、満月 (まんげつ) の古語は『望月 (もちつき / 餅つき) 』といい、望月氏も「月星紋 (家紋) 」を使用していたようです。
☆ ♪ ★ ♪ ☆ ♪
真田氏 → 海野氏、根津氏、望月氏という『滋野3家』は ほぼ同族で、その拠点は信濃国で、古代には「望月の牧」と呼ばれる馬の管理場があったといいます。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%85%E6%97%A8%E7%89%A7
ー・→
望月の由来ともなった「望月の牧」を始めとする御牧は、古く奈良時代から産する馬を朝廷に送られ、これらの産駒は途中の近江国甲賀村で休養や調教 (飼養牧) を行っていた。そこから望月氏と甲賀の地は古より関係があり、‥→‥→ 恩賞としてその後、信濃の望月氏の支流が甲賀の地で ‥→‥→
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9B%E6%9C%88%E6%B0%8F
ー・→
7世紀、
ヤマト朝廷の拠点が近江国にあった時 / 天智朝 (近江朝) の時代に起きた「白村江の戦い」に敗れた後 → 近江国 ~ 信濃国にかけて「牧」が急激に現れ、月星信仰を持つ駒人 (コマぴと) が日本に渡来したと云われています。

後ほど、甲賀望月氏 ~ 信濃望月氏に → 牧 → 柵 (さく) → 佐久? 通じたのかもしれません。
ー?→
上記の文を振り返ると?!
真田氏や海野氏が六文銭の家紋を使用するのは戦時用 (一時的) の お話であったけど、後世の「物語 / 文献」の影響から真田氏や海野氏と言えば『六文銭の家紋』と事が定着してしまった?
⇔ しかし、
(・・? もとはというと?!
真田氏 → 海野氏、根津氏、望月氏という『滋野3家』は、月星信仰に通づ「月星紋」を使用する駒人を祖とする一族という。
 ―…
―… →
→ →
→
(・・? その組合せは?!

既視感 (デジャブる) の気がしました。
既視感 (デジャブる) とは?

既 (すで) に、どこかで視 (み) た感 (ブ) る
こと。
━↓─━ ─扉─
─扉─ ━─↓━
━─↓━
実はというと、

打紙 (ウチカビ) = 冥銭 (あの世の紙銭) は、旧暦の7月15夜が近づくと販売を増します。
旧暦の7月13日に、あの世から御先祖様を「ウンケイ (お迎え) 」し → 7月15夜の『満月 ≒ 望月 (もちつき / 餅つき) 』になると、御先祖様を あの世に「ウ-クイ (お送り) 」します。
ー・→
旧暦の7月13日に、

門中 (むんちゅう) ≒ 親戚一同が集まり、仏壇にいる『トートーメー (御先祖様) 』に供え物をして 心の中で「うーとーとー」と唱え、あの世から御先祖様を「ウンケイ (お迎え) 」します。
ー・→
7月15夜の『満月 ≒ 望月 (もちつき / 餅つき) 』になると、

門中 (むんちゅう) が集まり、供物とともに打紙 (ウチカビ) を焚いて ↑ 煙りとともに ↑ 御先祖様を あの世に「ウ-クイ (お送り) 」します。その時も心の中で「うーとーとー」と唱えます。
☆ ♪ ★ ♪ ☆ ♪
(・・? もしかすると?!

打紙 (ウチカビ) も?!

「三途川の渡し賃」の役割を?と、
 ―…
―… →
→ →
→
通説では、トートーメー とは尊い方の前 ≒ 御先祖様と解釈されていますが、
⇔
異説として、トートーメー とはトト神 ≒ 月の神の前 と説もあります。

古代オリエントの「トト神」は「月の神」という属性を持ち、ギリシャ植民者がエジプトに普及させたとも云われています。
また、沖縄の幼児言葉では「お月さま」の事も「トートーメー」と言い、
心の中で唱える「うーとーとー 」の「うー」とは『オーマイゴット』の『オー』と同じで、
「うーとーとー 」とは古代オリエントの「あートト神よ」と言葉が訛化したもので、中国宗教の『儒教と道教』に触れて、儒教的な祖先崇拝や道教的な打紙 (ウチカビ) 儀式に変化したもの。そのほか、古代オリエントのライオンがシーサーに変化した。と説もあります。
━↓─━ ─扉─
─扉─ ━─↓━
━─↓━
琉球の王様は、

てだ子 (太陽の子) と云われ、
その後ろには、

∧ 斉場御嶽 (せーふぁウタキ) ♀ と久高島 (太陽の島) があり、太陽信仰をしていました。
斉場御嶽は知念半島にあり、その地は東御廻り (あがりウマーイ) という太陽信仰が盛んに行われていました。

その反対側には ⇔ 与勝半島があり、その地は旧暦の7月15夜に念仏廻りなどの月星信仰が盛んに行われています。
むかし、与勝半島の城 (グスク) と知念半島の城 (グスク) では『政略結婚』のようなものが行われていました。
与勝半島には勝連城 (かつれんグスク) がありました。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E9%80%A3%E5%9F%8E
9代目・勝連城主は茂知付 (もちづき) 氏で、茂知付も『満月 (望月 / 餅つき)』を意味していました。

その後、茂知付 (望月 / もちづき) 氏は阿麻和利 (あまわり) という人に亡ぼされます。
☆ ♪ ★ ♪ ☆ ♪
歴史本では、10代目の勝連城主・阿麻和利の妃は百度踏揚 (ももとふみあがり) と事がよく知られています。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E5%BA%A6%E8%B8%8F%E6%8F%9A
しかし、百度踏揚は2回目の結婚で、阿麻和利の1回目の結婚相手は『茂知付ヌル』という女性でした。
阿麻和利は、9代目・勝連城主の茂知付氏を亡ぼしたけど、茂知付氏の女性である『茂知付ヌル』を最初の妃にしていました。
*政略結婚
ー (・・? ー?→
実はその政略結婚の起源を辿ると、ギリシアにたどり着き、さらに辿ると?!

ペルシアにたどり着く? 云われています。


![]()
 んなわけない
んなわけない ![]()

おもう方もいるかもしれませんが、
「三途川の渡賃」の お話もギリシャ神話のアケローン川 (嘆きの川) が由来とされ、ギリシア人のアレキサンダー大王がペルシア帝国を亡ぼし → ギリシア人♂はペルシア人♀と政略結婚をし → 東征。その時代に仏教と出合い → 仏教は中国宗教の儒教と道教に吸収されて日本に渡りました。
 ―…
―… →
→ →
→
(・・? そのほか?

東御廻り (あがりウマーイ) という太陽信仰が盛んに行われていた知念半島の先には「海野」という部落があります。
(・・? 偶然にも?
真田幸村の古里は「東御市」になっている? とも云われています。

☆ ♪ ★ ♪ ☆ ♪
なぜか?

沖縄県旗は『月星紋』に似ている。