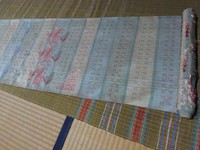叩いてポン
日本での 「絹糸」 の歴史は浅く、古くは主に『麻糸』が用いられていました。
古事記、日本書紀、埴輪図集、古語拾遺などの古い文献によると、

古代の衣服は、楮布、麻布、アシギヌ、藤布、科布、倭文布など‥ 用いられ、下人は染めた鹿の皮や動物の毛皮など‥ 着ていたといいます。

日本に古くから使用されていた布繊維は、楮 (こうぞ)、葛 (くず)、山藤 (やまふじ)、科木 (しなのき)、箆木 (へらのき) などの「樹皮繊維」⇔ 麻類などの『草皮繊維』が使用されていた。
古い糸として → 木の糸 (樹皮繊維) → 麻の糸 (草皮繊維) → 絹糸 (動物繊維) → 綿糸 (植物繊維) → という順序であったようです。
古くから、麻糸は租税の対象として生産され、麻繊維 (麻糸の原料) には「麻 (お)」 と『苧 (カラムシ) 』の2種があり、 今でいうと「麻 (お)」は大麻 (たいま) ⇔『苧 (カラムシ) 』は苧麻 (ちょま) を意味していました。
日本に自生し、繊維利用できる植物を「麻」と総称していたが、次第に海外より持ち込まれたアマ科の亜麻 (あま) やイラクサ科の苧麻 (ちょま) などを「麻」の名称に使うようになり、本来の麻 (お) = 大麻 (たいま) と苧 (カラムシ) = 苧麻 (ちょま) を区別するようになり、 「麻」を『苧』と表現する場合もあったようです。
(・・? むかし、今でいう麻糸でなくとも、繊維利用できる植物をすべて「麻」と呼んでいたようです。
ー(・・? ー・ー

苧麻 (ちょま) が生えている。

苧麻 (ちょま) の茎を使用するようだ‥

どうにかして、苧麻 (ちょま) の茎を‥

苧麻 (ちょま) の茎が?‥
( ゜_゜) ! あんな姿に、

おばあさんが、何かをしている。

苧麻 (ちょま) の糸を績 (う) む


ー(・・? ー・ー
今現在「麻」と呼ばれる繊維には数種類あり、 苧麻 (ちょま / ラミー)、亜麻 (あま / リネン)、大麻 (たいま / ヘンプ) 、黄麻 (こうま / ジュート) など‥ 30種類以上の繊維を麻糸 (あさいと / まし) の原料とし、日本の家庭用品質表示法によると、 苧麻 (ちょま / ラミー)、亜麻 (あま / リネン) の2種を指し、 かつて使用していた大麻 (たいま / ヘンプ) は指定外繊維になっているといいます。
主に、麻糸の繊維 (原料) には、苧麻 (ちょま / ラミー) がよく使用され、「麻」を『苧』と表現する場合もあったようです。
ー・ー
むかし、毛野国 (けぬこく) と科野国 (しなのくに) 辺りが『麻糸』生産が盛んであったようです。*毛野国 (けぬこく) は後ほど、上野国と下野国に分別し、科野国 (しなのくに) は信濃国に‥
当時、繊維利用できる植物をすべて「麻」と呼んでおり、科野国 (しなのくに) の語源 / 由来に、前述した 科木 (しなのき / 樹皮繊維) という説もあります。

信濃国の麻績 (おみ) 村がある。
古代の職業部に、麻糸を績 (う) む『麻績部 (おうみべ)』があり、その名残りかもしれません。
また毛野国 (けぬこく) の「毛」は「麻糸」の事だという人もいます。*そのほか、毛 (もう) = 「山」 説もある。
古代の毛糸は「羊毛」ではなく「麻糸」で、「木綿 (もめん)」と書いて『木綿 (ゆう)』 と読む『麻繊維』もあり、 *「毛糸」も『木綿 (ゆう)』も「木綿 (もめん)」ではなく『麻繊維』で績んだ糸でした。

古代人は、フジツル、アケビ、山桑、コウゾなどの繊維を撚り合わせて「毛糸」ほどの太さの糸を作り、それを編んで晒した「白たえ」を着ており、次第に大麻や苧麻の「麻糸」を使用していたという。
ー(・・? ー・ー
むかし、毛野国 (けぬこく) の南に武蔵 (むさし) という国 / 武蔵国がありました。武蔵国は、今の埼玉県、東京都、川崎市の一部辺りにあり、 *今では北関東と南関東の関係で、さいしょ頃、北関東が都会 ⇔ 南関東が田舎であったようです。
しだいに武蔵国は、麻糸や麻布、さらに時代が下ると絹糸、糸染など‥ 生産が発展して行きます。
ー・ー
少数説であるが、
武蔵国の語源 / 由来は、古代朝鮮語の 「苧種子 (モ・シシ) 」 が →『武蔵 (ムサシ) 』と訛化したという説もある。*敬遠されがちな説ですが、歴史家の鳥居龍蔵氏も、その説をとっています。

武蔵国の国府 (中心地) があった所が府中市になっており、白糸村、染屋村、布田村など‥ 調布も? 糸 / 布生産が盛んであったという。
武蔵国多磨村 → 北多摩郡 → 染屋村と白糸村は府中市 、武蔵国多磨村 → 北多摩郡 → 布田村 → 調布市 に、
そのほか、東京都港区麻布、埼玉 ← 前多摩 (さきたま) 、東京都世田谷区砧、川崎市麻生区柿生、多摩市、福生市 ← 総 (ふさ) 、 など‥ 糸 / 布生産の名残り地名のようにも思われます。
ー(・・? ー・ー
定かではなく、
麻の古語は総 (ふさ) → 福生 (ふっさ) ?
麻糸は 「染料」 で染めるのが難しく、柿渋 (タンニン成分) という『顔料』で染めていたと云われています → 川崎市麻生区柿生?
麻糸は綿糸と比べて肌触りが悪く、出来上がった / 完成品の麻布をわざと叩いて、アイロンがけのような作業をしていました。*ツヤ出しも、

完成した布地を叩く作業は『砧 (きぬた) 打ち』と呼ばれていました。
『砧 (きぬた) 打ち』→ 東京都世田谷区砧?
ー・ー
もったいない気もするけど、
新品の完成品を叩いて完成?‥

麻布を叩くと、肌触りがよくなるという。
古事記、日本書紀、埴輪図集、古語拾遺などの古い文献によると、

古代の衣服は、楮布、麻布、アシギヌ、藤布、科布、倭文布など‥ 用いられ、下人は染めた鹿の皮や動物の毛皮など‥ 着ていたといいます。

日本に古くから使用されていた布繊維は、楮 (こうぞ)、葛 (くず)、山藤 (やまふじ)、科木 (しなのき)、箆木 (へらのき) などの「樹皮繊維」⇔ 麻類などの『草皮繊維』が使用されていた。
古い糸として → 木の糸 (樹皮繊維) → 麻の糸 (草皮繊維) → 絹糸 (動物繊維) → 綿糸 (植物繊維) → という順序であったようです。
古くから、麻糸は租税の対象として生産され、麻繊維 (麻糸の原料) には「麻 (お)」 と『苧 (カラムシ) 』の2種があり、 今でいうと「麻 (お)」は大麻 (たいま) ⇔『苧 (カラムシ) 』は苧麻 (ちょま) を意味していました。
日本に自生し、繊維利用できる植物を「麻」と総称していたが、次第に海外より持ち込まれたアマ科の亜麻 (あま) やイラクサ科の苧麻 (ちょま) などを「麻」の名称に使うようになり、本来の麻 (お) = 大麻 (たいま) と苧 (カラムシ) = 苧麻 (ちょま) を区別するようになり、 「麻」を『苧』と表現する場合もあったようです。
(・・? むかし、今でいう麻糸でなくとも、繊維利用できる植物をすべて「麻」と呼んでいたようです。
ー(・・? ー・ー

苧麻 (ちょま) が生えている。

苧麻 (ちょま) の茎を使用するようだ‥

どうにかして、苧麻 (ちょま) の茎を‥

苧麻 (ちょま) の茎が?‥
( ゜_゜) ! あんな姿に、

おばあさんが、何かをしている。

苧麻 (ちょま) の糸を績 (う) む


ー(・・? ー・ー
今現在「麻」と呼ばれる繊維には数種類あり、 苧麻 (ちょま / ラミー)、亜麻 (あま / リネン)、大麻 (たいま / ヘンプ) 、黄麻 (こうま / ジュート) など‥ 30種類以上の繊維を麻糸 (あさいと / まし) の原料とし、日本の家庭用品質表示法によると、 苧麻 (ちょま / ラミー)、亜麻 (あま / リネン) の2種を指し、 かつて使用していた大麻 (たいま / ヘンプ) は指定外繊維になっているといいます。
主に、麻糸の繊維 (原料) には、苧麻 (ちょま / ラミー) がよく使用され、「麻」を『苧』と表現する場合もあったようです。
ー・ー
むかし、毛野国 (けぬこく) と科野国 (しなのくに) 辺りが『麻糸』生産が盛んであったようです。*毛野国 (けぬこく) は後ほど、上野国と下野国に分別し、科野国 (しなのくに) は信濃国に‥
当時、繊維利用できる植物をすべて「麻」と呼んでおり、科野国 (しなのくに) の語源 / 由来に、前述した 科木 (しなのき / 樹皮繊維) という説もあります。

信濃国の麻績 (おみ) 村がある。
古代の職業部に、麻糸を績 (う) む『麻績部 (おうみべ)』があり、その名残りかもしれません。
また毛野国 (けぬこく) の「毛」は「麻糸」の事だという人もいます。*そのほか、毛 (もう) = 「山」 説もある。
古代の毛糸は「羊毛」ではなく「麻糸」で、「木綿 (もめん)」と書いて『木綿 (ゆう)』 と読む『麻繊維』もあり、 *「毛糸」も『木綿 (ゆう)』も「木綿 (もめん)」ではなく『麻繊維』で績んだ糸でした。

古代人は、フジツル、アケビ、山桑、コウゾなどの繊維を撚り合わせて「毛糸」ほどの太さの糸を作り、それを編んで晒した「白たえ」を着ており、次第に大麻や苧麻の「麻糸」を使用していたという。
ー(・・? ー・ー
むかし、毛野国 (けぬこく) の南に武蔵 (むさし) という国 / 武蔵国がありました。武蔵国は、今の埼玉県、東京都、川崎市の一部辺りにあり、 *今では北関東と南関東の関係で、さいしょ頃、北関東が都会 ⇔ 南関東が田舎であったようです。
しだいに武蔵国は、麻糸や麻布、さらに時代が下ると絹糸、糸染など‥ 生産が発展して行きます。
ー・ー
少数説であるが、
武蔵国の語源 / 由来は、古代朝鮮語の 「苧種子 (モ・シシ) 」 が →『武蔵 (ムサシ) 』と訛化したという説もある。*敬遠されがちな説ですが、歴史家の鳥居龍蔵氏も、その説をとっています。

武蔵国の国府 (中心地) があった所が府中市になっており、白糸村、染屋村、布田村など‥ 調布も? 糸 / 布生産が盛んであったという。
武蔵国多磨村 → 北多摩郡 → 染屋村と白糸村は府中市 、武蔵国多磨村 → 北多摩郡 → 布田村 → 調布市 に、
そのほか、東京都港区麻布、埼玉 ← 前多摩 (さきたま) 、東京都世田谷区砧、川崎市麻生区柿生、多摩市、福生市 ← 総 (ふさ) 、 など‥ 糸 / 布生産の名残り地名のようにも思われます。
ー(・・? ー・ー
定かではなく、
麻の古語は総 (ふさ) → 福生 (ふっさ) ?
麻糸は 「染料」 で染めるのが難しく、柿渋 (タンニン成分) という『顔料』で染めていたと云われています → 川崎市麻生区柿生?
麻糸は綿糸と比べて肌触りが悪く、出来上がった / 完成品の麻布をわざと叩いて、アイロンがけのような作業をしていました。*ツヤ出しも、

完成した布地を叩く作業は『砧 (きぬた) 打ち』と呼ばれていました。
『砧 (きぬた) 打ち』→ 東京都世田谷区砧?
ー・ー
もったいない気もするけど、
新品の完成品を叩いて完成?‥

麻布を叩くと、肌触りがよくなるという。