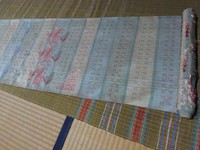南の音 と 北の音
林 (リン) さん と 林 (はやし) さん。
いました。
林 (リン) さんは音読み、
林 (はやし) さんは訓読み。
(・・? やはり何となく、音読みは中国の音 (オン) 、訓読みは日本の音 (おと) ようにも聞こえます。
ー・ー
漢字の音 (オン / おと) には音読みと訓読みの2つありました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e9353718.html そして、その訓読みは音読みを解 (わか) るようにした音 (おと) なので、訓読みよりも音読みの方が古いように見えます。
また、その音読みには「呉音、漢音、唐音」とあり、日本への伝来は『呉音 → 漢音 → 唐音』の順序になっており、呉音は飛鳥時代、漢音は奈良 ~ 平安時代ころ、唐音は平安 ~ 鎌倉時代ころ。普及したようです。
‥>中国と日本の時代‥>
隋 (581-618) ー 飛鳥時代、
唐 (618-907) ー 飛鳥 - 平安時代、
宋 → 北宋 (960-1127) と南宋 (1127-1279) ー 平安 - 鎌倉時代。
‥>
(・・;) てっきり、
漢音は漢の時代、唐音は唐の時代。伝来したと思っていましたが、違っていました。
とりわけ、日本に古くから伝来したのは呉音で、その呉音はあの時、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8832692.html 猫 (ミョウ) とともにやって来ました。
*猫 (ミョウ) は呉音、猫 (ビョウ) は漢音、訓読みでは猫 (ねこ) 。
そのとき、猫 (ミョウ) はわき役で、主役は仏様 (仏像) でした。

6世紀ころ、印度 → 中国 → 朝鮮半島の百済を経て 正式に 仏教 (仏様) が日本にやって来たと云われています。
朝鮮半島の百済に仏教が普及した時代の中国は、華北勢力と華南勢力の争う「南北朝時代」で、

百済仏教は華南勢力 = 南朝勢力の『呉』と呼ばれる南方の影響を強く受けていたようです。*呉音は南の音
 ―…
―… →
→ →
→
(・・;) ところで ;
日本へ初めて来た仏様 (仏像) は難波の川に棄てられていました。

http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12061956750.html 日本への 「仏教」 の導入 / 賛否を巡る 物部氏と蘇我氏 による『崇仏廃仏論争』をしていました。
そのとき棄てられた仏様 (仏像) の名前は阿弥陀様でした。
阿弥陀様は、
呉音では阿弥陀如来 (アミダニョライ)
漢音では阿弥陀如来 (アビダジョライ)
お釈迦様は、
呉音では釈迦如来 (シャカニョライ)
漢音では釈迦如来 (セキャジョライ)
━↓─━ ─扉─
─扉─ ━─↓━
━─↓━
時代は下り、
平安時代 (中国は唐の時代) に桓武天皇より、これからは『呉音ではなく漢音を使用するように』と、御触れが出ました。
呉音は南の音でしたが ⇔ 唐は漢音 (北の音) を利用する国でした。
ー?ー
中国の南北朝時代に華北地方は、北魏という国が統一しましたが、北魏は北方の遊牧騎馬民族・鮮卑 (せんぴ) 族の拓跋氏によって建てられた国。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/北魏
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/鮮卑
その北魏から、唐という国が派生しているので、唐は北方の漢音を使用する国であったようです。
呉音は南の音 ⇔ 漢音は北の音
ー・→
平安京の桓武天皇は、古い音 (呉音) を廃止し ⇔ 新しい音 (漢音) を普及させようとしていたようにも思われます。
(・・;) ところが、
ある問題が発生していました。
例えば、
仏教経典の「お経」を読むとき、
呉音では南無阿弥陀仏 ♪ナムアミダブツ♪
漢音では南無阿弥陀仏 ♪ナブアビダブツ♪
唐音では南無阿弥陀仏 ♪ナムオミトフ♪
など、

音が変化すると? 長いお経の ♪リズム♪ がおかしくなってしまいます。
ー(・・? ー・ー
そのためか?
仏教用語では呉音 ⇔ 日常生活では漢音が使用されている場合が見られます。
[呉音 / 漢音]
経典 (キョウテン) / 経典 (ケイテン) 、
食堂 (ジキドウ) / 食堂 (ショクドウ) 、
境内 (ケイダイ) / 境内 (ケイナイ) 、
利益 (リヤク) / 利益 (リエキ) 、
月光 (ガッコウ) / 月光 (ゲッコウ) 、
日光 (ジッコウ) / 日光 (ニッコウ)
など。